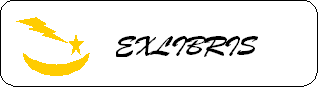これが歌えなくては(吉野秀雄『やわらかな心』)
真命(まいのち)の極みに堪へてししむらを敢えてゆだねしわぎも子あはれ
これやこの一期のいのち炎立ち(ほむらだち)せよと迫りし吾妹よ吾妹よ
ひしがれてあいろもわかず堕地獄のやぶれかぶれに五体震はす
この三首を山本健吉編『日本の恋の歌』(講談社現代新書)で読んでから、作者である吉野秀雄の名前が頭に染みついてしまった。
病妻が亡くなる前夜、死を覚悟でおこなった夫婦最後の交合いを詠ったものである。私がつべこべ言うより、山本健吉の解説をここにあげておこう。
『――これほど厳粛なものとしてよまれた男女交合の歌は、ほかにないのです。しかも、そこには、そのことをおぼめかし、美化して歌おうとする配慮の一点の余地もないのです。その命の合体の一瞬に、いささかの享楽的要素もないのです。――〈中略〉――こういう歌は、めったに作られるものではありません。こういう歌をつくるには、やはり作者の大きな勇気がいります。人生の厳粛な真実に、おめずに立ち向かおうとする勇気です。』
その吉野秀雄のエッセイ集『やわらかな心』(講談社文庫 昭和五十三年初版)を入手した。
予想通り、子供のように純な魂の持ち主である。「自歌解説は控えておく」などというもったいぶった態度はどこにもない。自分が納得できる歌ができれば興奮気味にその良さを説明し、またそれを誉められれば、臆面もなく人の賛辞を引用して喜こんでいる様は、型通りの謙遜よりはるかに清々しい。
そんな裏も表もない書きぶりだけに、みずからがリューマチで寝たきりになったうえ、絵描きとして独り立ちしかけた息子が突如発狂するという人生の地獄を綴った箇所では、ページをめくる手がついに動かなくなってしまった。読むのがつら過ぎて、先へ進めないのである。本に接していて、こんな経験ははじめてだ。
『せがれの哀しみと自分の哀しみとを主題にして、歌も作ろう。これが歌えなくてはほんものの歌よみとはいえないだろう。あわれなせがれは、わたしをほんものの歌読みにするためのごとくに狂気してしまったのだろうか。ナムアミダブツ、ナムアミダブツ。』
悲しみと不安のさなか、彼はあえて歌よみとしての決意を表白する。
引用文の最後に念仏が出てきたが、吉野は良寛への熱烈な敬慕の思いも語っている。
病没後三十五年、彼は歌と念仏を通じて良寛の人格に近付き、いまごろは、ときに蓮を同じくして、あこがれの師との対話を楽しんでいるのではないか。
ぜひそうあって欲しいと願わずにいられない。
|